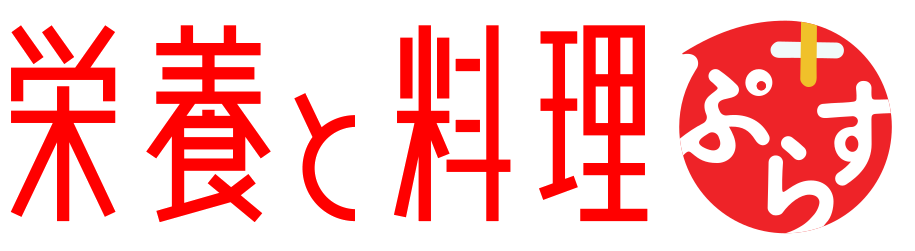北マケドニア共和国
文と写真/岡本啓史(国際教育家)
Добро утро
北マケドニアでは、朝は「Добро утро(ドブロ ウトロ)=おはようございます!」というあいさつから始まります。
北マケドニアは、どこにある?
国名を見ても「え、どこ?」「“北”ということは“南”や“中央”マケドニアもある?」「もしかして、コーヒーのマケドニア風?」など、どこにあるのかさえ見当がつかない日本人が少なくないかもしれません。
北マケドニア共和国は、ヨーロッパ南東部、バルカン半島の中心に位置し、歴史と自然が美しく融合する国。国土の約80%が山と丘でおおわれ、3つの大きな自然湖があります。中でもオフリド湖は、北マケドニアとアルバニアにまたがる約400万年前から存在する世界最古級の湖の1つで、美しい自然景観による自然、そして周囲にある建築物など文化が今も残っていることから、世界自然・文化複合遺産にも登録されています。
また、ローマ帝国やオスマン帝国の影響を受けてきた北マケドニアは、東洋と西洋が交わる文化の十字路ともいえます。そのため、さまざまな民族や宗教が共存し、多様な伝統と料理が今も受け継がれています。また、都市部ではカフェ文化が栄え、農村部では家庭のレシピが根強く残るなど、多層的な魅力があります。
ちなみに、「ギリシャ系マケドニア」に住む人々は、かつてマケドニア語を話していましたが、占領下で名前を変えさせられ、ギリシャ語の使用を強制された歴史があります。「北マケドニア」と国名を改めたのはEU加盟に向けた一歩でしたが、現在も未だ加盟には至っていません。美しく豊かな自然に囲まれた国には、静かに語られる複雑な歴史が息づいています。

北マケドニアとアルバニアにまたがる「オフリド湖」は、世界自然・文化複合遺産にも登録されている。
今回は、そんな北マケドニア出身のナターシャさんの朝ごはんをご紹介します。
ナターシャさんは二児の母親。ドイツ語教師として働き、家事や仕事が忙しくても子どもとの時間をたいせつにしています。また、ヨガと瞑想を実践し、絵やカリグラフィー(日本でいう習字)を描き、異文化に深く関心を寄せる、感性豊かな女性です。
北マケドニアの伝統的な飲み物「マケドニアコーヒー」とは?
ナターシャさんの朝は、多くの北マケドニア人と同じく、マケドニアコーヒーとともに始まります。
アラビカ豆を細かく挽き、「џезве(ジェズヴェ)」と呼ばれる小なべで煮出すマケドニアコーヒーは、トルコ式にも似ていながら独自の風味と文化を持っています。飲み終わったあとの招待客のカップをひっくり返してさまし、残ったコーヒーの模様から招待主が運勢を占うという「カップ占い」も文化の1つです。味わい深いだけでなく、おもてなしのひとときに使われるコーヒーといっしょに、会話が自然と弾みます。


〈左〉ナターシャさんと朝のコーヒー。 〈右〉コーヒーを煮出すジェズヴェ。
北マケドニアの朝食は、揚げ焼パンに野菜、チーズ、果物…
今回ナターシャさんが用意してくれた朝食は、シンプルでありながら栄養バランスに優れ、彩りも豊か。

ナターシャさんの朝ごはんは、シンプルかつカラフル。
そのメニューの中身をご紹介しましょう。
- アイヴァル(Ajvar) 赤パプリカとナスを焼いてペースト状にした伝統の保存食。各家庭でレシピが異なり、秋には家族総出で大量に仕込む光景も見られます。作る量が多すぎて、親戚じゅうに配るほどなのだとか。フェタチーズやパンといっしょに食べると絶品。
- プルジェニ・レプチニャ(Пржени лепчиња) 卵液に浸したパンを揚げ焼きにする家庭料理。見た目はフレンチトーストに似ていますが、甘くするのではなく、塩味で仕上げるのが北マケドニア流。子どものころ、学校へ行く前によく食べたという人も多い、ノスタルジックな一品です。
- 新鮮な野菜とチーズ トマト、ピーマン、フェタチーズ、オリーブは地中海的食文化の影響を受けた定番。夏の朝に庭で収穫した野菜をそのまま食卓に並べることも多く、季節を感じながら食べることができます。
- ブレック(Burek) 層状の生地にチーズ、肉、ほうれん草などを詰めて焼いた、サクサクのパイ。オスマン帝国の影響を受けたバルカン料理の代表格で、外はパリッと、中はジューシーで満足感たっぷり。学校や仕事前に買って歩きながら食べる「マケドニア式ファストフード」としても人気です。




〈左上〉パプリカとナスのペーストのアイヴァル(Ajvar)、〈右上〉 北マケドニア風の塩味のフレンチトースト「プルジェニ・レプチニャ」〈左下〉シンプルでフレッシュなチーズや野菜た〈右下〉北マセドニアのパイ「ブレック」。
北マケドニアと日本のつながり
一見すると遠く離れているように思える日本と北マケドニアですが、意外な共通点や交流もあります。
- 「太陽の国」つながり 両国の国旗には太陽が描かれており、それぞれのアイデンティティの象徴とされています。
- 穏やかで親しみやすい国民性 お互いの文化に敬意を払い、相手との調和をたいせつにする価値観があります。
- 保存と発酵を生かした和食とバルカン料理の共鳴 発酵食品や保存食が多く使われており、日本のみそや漬物文化とどこか似た親近感があります。たとえば、上述のアイヴァル(パプリカ・なすペースト)のように「時間と手間をかける」食への姿勢に共鳴があります。


〈左〉北マケドニアの国旗。〈右〉日本の国旗。
冬のモンゴル、スペイン語の縁でつながったナターシャさん
ナターシャさんと出会ったのは、馬と草原の国・モンゴルでした。
私は2015年から2018年までモンゴルで暮らしており、ボリビアやチリなどスペイン語圏出身の人やスペイン語を話す人が集まる「ラテン交流会」に定期的に参加していました。冬のモンゴルの気温はマイナス40度以下になり、その極寒の季節を乗り越えるには、人の温もりがなによりの支え。ラテンの陽気な音楽と情熱的なムードが、心と体を温めてくれたのです。
そんなある日、スペイン語に関心を持っていた北マケドニア出身のナターシャさんが交流会に参加することとなりました。モンゴルという、各参加者にとって‟異国の地”で交わされた会話や笑顔は特別でした。以来、その場はますます多国籍なムードが醸成され、多様な文化が交差する「小さな地球」のような空間となりました。
厳しい寒さの中、家族ぐるみで親密な関係を築いたナターシャさんは、何年経っても連絡をとり合うたいせつな友人であり、今回の朝ごはん企画でも快く協力してくれました。
ナターシャさんの朝ごはんは、栄養をとるための食事というだけでなく、故郷の思い出や文化、家族のぬくもりの記憶が詰まった媒体ともいえます。北マケドニアの朝は、温かく穏やかで、人と人とのつながりに満ちたひとときのようです。
「北マケドニアでは、コーヒーは一人で飲むことはなく、隣人や友人、家族といっしょに楽しむもので、人と人をつないでくれる存在です」――ナターシャさんはそう教えてくれました。
忙しさのあまり、つい”時短”を求めてしまいがちですが、一息ついてだれかといっしょにゆっくり過ごす時間が人生にとっては重要であることを改めて感じさせられました。

モンゴルの寒い冬(2017年)をそれぞれの家族とともに乗り越えた、多国籍の仲間たち。立っている私(右)と写真中央でワイングラスを持つナターシャさん。
日本ではあまりなじみのない北マケドニアですが、この記事を通じて、少しでもその魅力や人の温かさを感じていただけたら幸いです。
次回はどの国の朝ごはんが登場するのか、どうぞお楽しみに!

| 【筆者プロフィール】岡本啓史(おかもと・ひろし)●国際教育家、生涯学習者、パフォーマー。これまで国連やJICA等で5大陸・45カ国の教育支援を実施。ダンサー、役者、料理人、教師の経歴も持つ。学びに関するブログを5言語で執筆し、ライフスキル教育、講演活動、グローバル学び舎3L-ミエル運営など、日本内外で国際理解・幅広い学びやウェルビーイングの促進に注力中。著書『なりたい自分との出会い方:世界に飛び出したボクが伝えたいこと』(岩波書店)『せかいのあいさつ』全3巻(童心社)監修。サイト/SNS:https://linktr.ee/mdhiro |