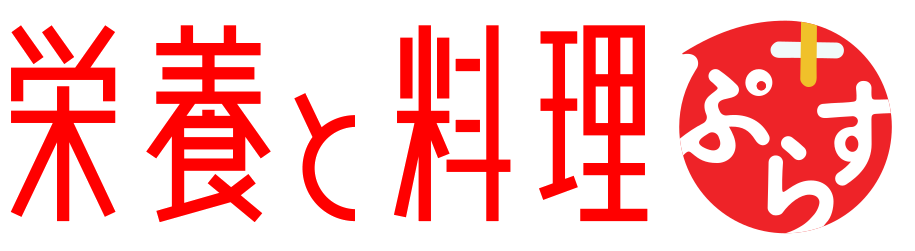スイス
文と写真/岡本啓史(国際教育家)
Bonjour!
スイスには ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語という4つの公用語があります。九州ほどの国土で4つもの言語が共存しているのは、まさにスイスの言語的多様性を象徴しています。ジュネーブなど、スイスのフランス語圏では、朝は「Bonjour!(ボンジュール)」のあいさつで始まります。家族によっては「Bien dormi?(よく眠れた?)」と質問をしたり、カジュアルな「Coucou!(ククー)」というかけ声使うこともあります。
日本語で、前から読んでも後ろから読んでも「スイス」という、この国について思いつくことは? アルプスの少女ハイジ、銀行、時計製造、永世中立国、エーデルワイス(国花)…… 出てくるキーワードは意外と多いかもしれませんが、食文化についてはどうでしょうか。
今回は、そんなスイスから 多文化が共生する家族の朝ごはんを紹介します。



スイス南部・ヴァレー地方のアルプスの四季を感じさせる風景。
今回紹介するのは、スイス人のスティーブンさんと、フランス人とチリ人の親に生まれたテレシータさん夫妻です。スティーブンさんは、母親がローザンヌ(フランス語圏)出身、父親がチューリッヒ(スイスドイツ語圏)出身のため、両方の言語を話しながら育ちましたが、長年ジュネーブで暮らしていたため、今でも自分自身はフランス語ネイティブ(母語者)だと考えています。二人は海外での生活から戻り、現在スイスのジュネーブで、6歳のラファエルくんと4歳のアメリちゃんという2人の子どもとともに、多言語が飛び交う家庭で暮らしています。


〈1枚目〉スティーブンさんと子どもたち。〈2枚目〉テレシータさんと子どもたち
スイスの栄養たっぷり朝ごはん「ビルヒャーミューズリー」とは?
料理好きなスティーブンさんにとって、朝ごはんはとてもたいせつな時間です。一方でテレシータさんは、朝は食欲がなく、おいしいカフェオレを飲んで一日を始めます。
スティーブンさんがよく作るのは「ビルヒャーミューズリー(Bircher Müesli)」、またはビルヒャーです。この料理は世界じゅうで知られていますが、じつはスイス発祥とのこと(名称はスイス・ドイツ語に由来します)。
20世紀初頭、チューリッヒの医師ビルヒャー博士が栄養失調の患者を回復させるために、アルプスの牧人の食事からヒントを得て、リンゴのすりおろし・オーツ麦・レモン果汁・ナッツ・練乳を混ぜ合わせたのが始まりでした。患者は驚くほどの早さで回復し、「ビルヒャー」は栄養価の高い朝食として広まりました。
現在ではさらに多様化し、カフェやレストランでは健康的な朝食として人気があります。一般的な市販品は、プレーンヨーグルト、フルーツ、グラノーラやオーツ、種実などで構成され、ヨーグルトのなめらかさが特徴です。親戚の家ではなんとホイップクリームを加えることあり、濃厚で絶品ながら少し“罪深い”味になるのだとか。
スティーブンさんは家にある果物をふんだんに使い、フラックスシード(亜麻仁/アマニ)、チアシード、砕いたアーモンド、オーツやグラノーラ(穀物やドライフルーツなどを混ぜて焼き固めたもの)などを加えて、ビタミンたっぷりの朝をスタートします。




果物を切り、穀物を次々加え、ヨーグルトをかけ、種実をふりかけて完成したスティーブンさんの「ビルヒャーミューズリー」。
スイスやヨーロッパの多くの家庭と同じく、朝のもう一人の主役は「コーヒー」です。スティーブンさんはブラックで、テレシータさんはオーツミルクを加えて飲みます。焙煎したコーヒー豆を買ってきて直前に挽くのがこだわりで、その香りとともに一日が始まります。
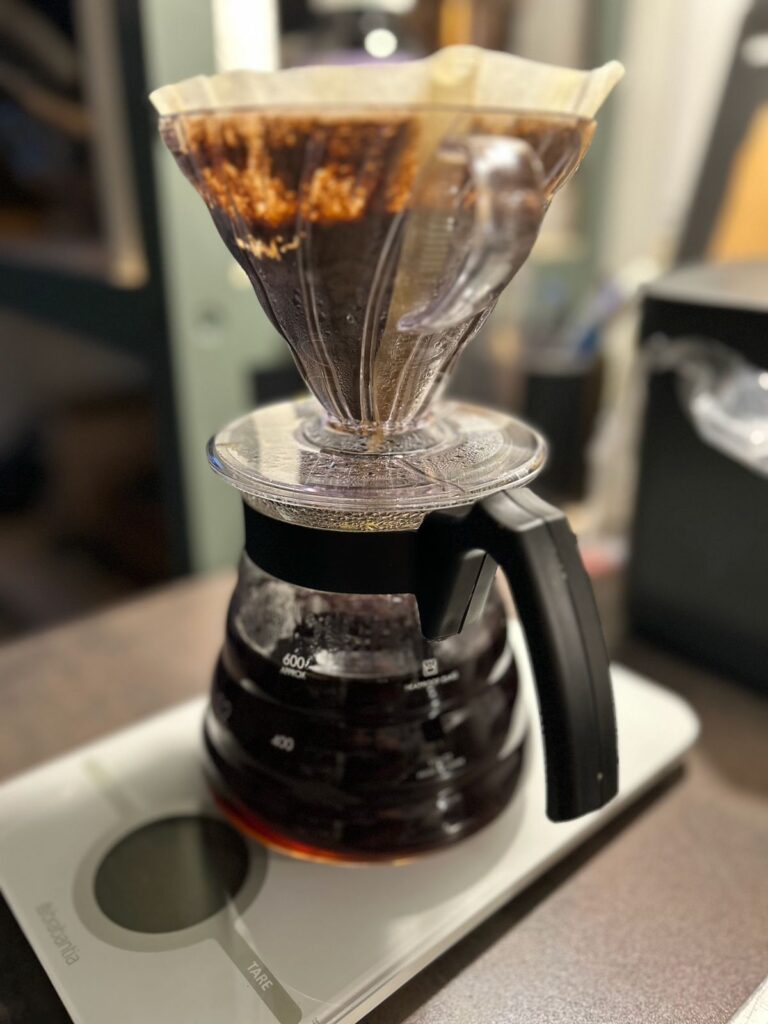
朝の主役・コーヒー。
一方、ラファエルくんとアメリちゃんはスペルト小麦(小麦粉の原種にあたる古代穀物で品種改良や遺伝子組み換えがほとんどされていないもの)のシリアルや穀物フレークにミルクをかけて食べるのが大好き。
スイスは酪農が盛んで、良質な牛乳で知られています。家庭では大量の牛乳を常備。朝食のシリアルは甘くない全粒タイプが基本で、ケロッグなどの甘い製品はバカンスのときだけ特別に食べるそうです。
スイスの伝統的なパン「トレッセ」を楽しむ朝のひととき
子どもを学校に送り出したあと、テレシータさんはおなかが空いてくるので、よく「トレッセ (Tresse)」と呼ばれるスイスの伝統的なパンをトーストして味わいます。多様な文化が交わるスイスを象徴したような三つ編み型のパンを前に、ようやく穏やかな時間を過ごします。バターとジャムといっしょに 食べるのが定番のようですが、テレシータさんはカッテージチーズと果物をのせるのが好みだそうです。


トレッセ(Tresse)をスライスし、カテージチーズやベリーをのせて食べる。
スイスと日本は似ている?ーー自然環境や独自の伝統文化に見える共通点
・ 両国ともに山がちで険しい地形が多く、農業が可能な場所も限られています。日本の本州にも「日本アルプス」と呼ばれる、北・中央・南の3つの山脈群があります。
・ 天然資源が乏しいため、勤勉な国民性と技術で国を発展させてきました。一方で、両国とも少子高齢化が進んでいます。
・ 両国とも時に厳しく、時に残酷な自然の力を受け入れ、敬意を払う文化を育んできました。たとえばスイスでは、冬の終わりに「ボンオム・イヴェール/bonhomme hiver(冬の男)」という藁人形を燃やして春を迎える祭りや、悪霊を追い払う鐘の行事/Chalandamarz(シャランダマルツ)など、自然の厳しさに寄り添う伝統が今も残っています。
出会いはモザンビークでの国際協力。料理を持ち寄って、家族ぐるみでお付き合い
私とスティーブンさん一家との出会いは、アフリカ・モザンビークでの滞在中でした。
スティーブンさんとは国際協力の仕事でつながり、家族ぐるみの交流が始まりました。集まりでは、フランス語・スペイン語・英語・ポルトガル語・日本語が飛び交い、文化も言葉も違うのに、多様な食を通していろいろな人の心がつながっていました。中でも、お互いの国の料理を持ち寄る食事会は、今も忘れられない思い出です。


スティーブンさん(右端)の家で。右から3人目がテレシータさん。左端は筆者。世界各国の料理が並んだ食卓。
スイスの朝ごはんは、単なるレシピやエネルギー補給ではなく、その国の歴史・多文化・家族の姿を映し出しています。香り立つ挽きたてのコーヒー、果実の甘みと彩りが広がる栄養たっぷりのビルヒャーミューズリー、そして安らぎのひとときをもたらす三つ編み模様のトレッセパン……。どれもが物語を紡ぎ、家族や文化をつなぐ象徴となっています。
遠く離れても、スティーブンさん一家とのつながりが続いているように、朝ごはんは文化と世界をつなぐ入口になります。 朝ごはんを通して世界を旅するこのシリーズ。次は、どんな国のどんな人の朝に出会えるのでしょうか。
それでは、また次回の“世界の朝ごはんめぐり”でお会いしましょう!

| 岡本啓史 おかもとひろし🟡国際教育家、生涯学習者、パフォーマー 世界5大陸で暮らし、国連やJICAを通じて50カ国以上で教育支援に携わる。ダンサー、俳優、星付きレストランのシェフ、教師など多彩な経歴を持つ。 異文化で学び続けた海外18年を経て、2024年に帰国し、神戸でグローバル学び舎3L-ミエルを設立。「多様性と幅広い学び」を次世代へつなぐことを使命に、教育、食文化からウェルビーイングなど幅広いテーマで講演・研修・執筆を行う。5言語で学びに関するブログでゆるく発信中。徳島文理大学特任教授。日本SEL学会理事。 著書『なりたい自分との出会い方』(岩波書店)『せかいのあいさつ』全3巻(童心社)監修。 サイト/SNS:https://linktr.ee/mdhiro |