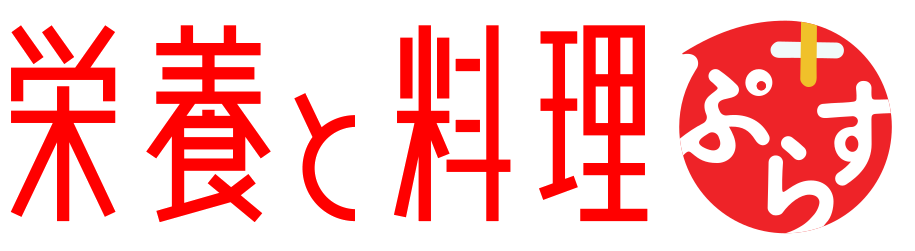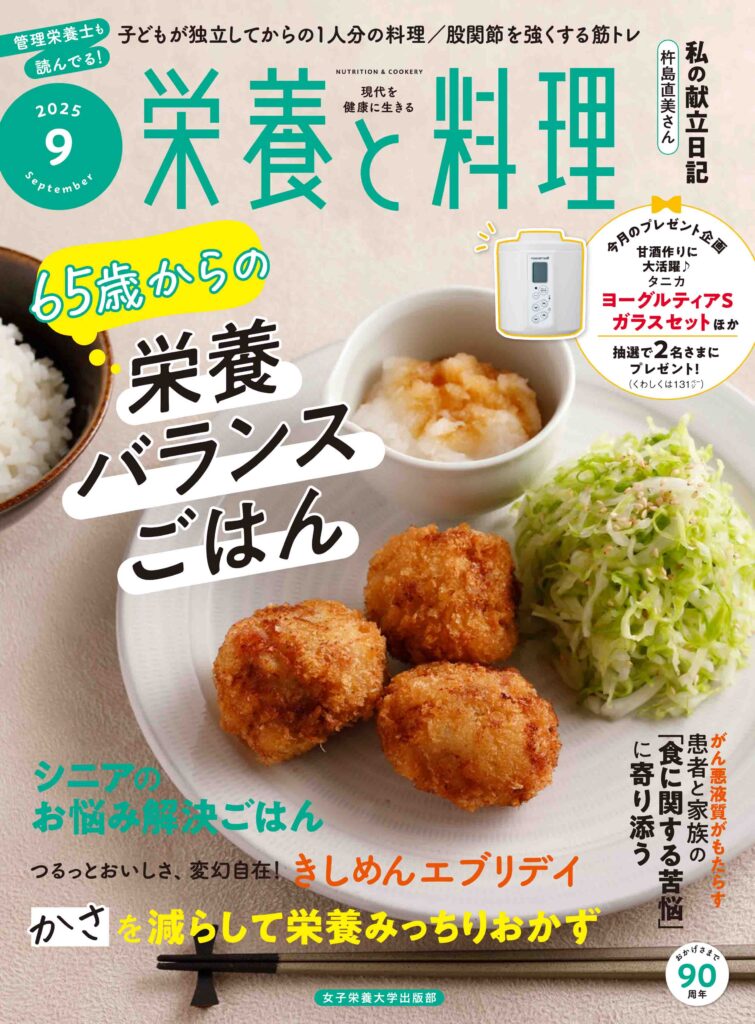ナミビア
文と写真/岡本啓史(国際教育家)
Moro!
「モロ!」は南西アフリカにあるナミビアで使われているヘレロ語(Otjiherero)の朝のあいさつです。
ヘレロ語とは、ナミビアの多くの地域言語の1つで、砂漠やサバンナに暮らすヒンバ族やヘレロ族などがおもに使用しています。
現在のナミビアの公用語は英語ですが、1990年に南アフリカから独立するまではアフリカーンス語やドイツ語も使われていました。その重層的な歴史が、風景や言葉、文化の多様なコントラストを生み出しています。
さて、そんなナミビアですが、この国のことをどれくらいご存じでしょうか。まず思い浮かぶのは「ナミブ砂漠」かもしれません。果てしなく続く砂丘や、大西洋へと沈む夕日、星空の下のサファリを思い出す人もいるでしょう。けれども、砂漠や自然、野生動物だけがナミビアの魅力ではありません。もう一歩、その奥にある人々の暮らしや文化を深掘りしていきましょう。



ナミビアには、独自の生活様式を守り続ける半遊牧民・ヒンバ族も暮らしています。彼らは、赤土(オーカー)と牛脂を混ぜたペーストを体や髪に塗る独特の美の習慣で知られ、伝統的な装飾品を身につけています。
今回は、ヒンバ族の出身で、みずからの文化に誇りを持つヴィンセントさんの朝ごはんを紹介します。

ナミビア出身のヴィンセントさん。
ヴィンセントさんは、ツアーガイド兼ドライバーとして世界じゅうからやって来る旅行者を迎えています。「いつか最高のガイドの一人となって、自分の会社を持ちたい」と夢を語る彼は、ナミビアの魅力を案内することに情熱を注いでいます。そんな彼の朝食はどのようなものでしょうか。
ナミビアの朝食文化|ヒンバ族の一日を支える、とうもろこしがゆ「オシフィマ」

朝食の「オシフィマ」とヴィンセントさん
村での暮らしでも、ガイドとして働く日でも、彼の朝はいつも日の出とともに始まります。シンプルな朝食が、一日のエネルギー源となっています。
彼の朝食は「オシフィマ」と呼ばれるとうもろこしがゆです。とうもろこし粉、バター、塩、ナミビアの伝統食品ともいえる発酵バターミルク(オマエレ)を加えたもので、ときにはエネルギー補給のためブラウンシュガーを加えることもあります。
粉をなべに入れたら、絶えずかき混ぜながらバター、塩、オマエレを加えます。その根気とリズムは、幼いころから受け継がれてきた生活の知恵だといいます。
一見すると質素に見えるかもしれませんが、ヒンバの人々にとってこれは、伝統と生きる力を支えるたいせつな食事です。ナミブ砂漠のデッドフレイの風景のように、過酷な環境の中で培われた知恵が息づいているといえるでしょう。
「ヴィンセントさんにとってオシフィマとは?」とたずねたところ、「シンプルですが、私に力を与えてくれ、故郷や仲間、そして自分のルーツを思い出させてくれる。どこへ行ってもオフィシマを食べています」という言葉が返ってきました。



ナミビアの若きガイド、ヴィンセントさんと訪ねたヒンバ族の村──伝統が息づく暮らしに触れて
私がヴィンセントさんと出会ったのは、現地ナミビアで彼がガイドしてくれたときでした。
観光地を巡るだけでなく、現地の文化も知りたいと伝えると、彼は観光客の足が届かないヒンバ族の村へ案内してくれました。そこでは、子どもたちがオシフィマを作り、女性たちが装飾品を身につけ、暮らしの中に伝統が息づいていました。
ヴィンセントさんとともに「ヒンバの踊り」を踊り、料理を作り、未来について語り合った時間は、今も心に残っています。彼の温かさとプロとしての誠実さが、私をまるで自宅にいるかのように安心させてくれました。
彼の夢である「 一流のガイドとなり会社を持つこと 」 は、伝統と未来をつなぐナミビアの若者たちの希望そのものでした。




ナミビアの道中で出会ったヒンバ族の女性──“裸”の意味と装飾が語るアイデンティティ
ヒンバ村を出るさい、ある女性に「おなかが痛いので病院に行きたい」と頼まれたので、私たちは車でいっしょに都市部まで向かいました。
道中、彼女はアイデンティティや近代化、教育について語ってくれましたが、最も印象的だったのは次の言葉です。
「服を着ていなくても裸だとは感じません。でも装飾品をつけていないと、裸だと感じるのです。それが私たちのアイデンティティだから。」
文化の違いが世界の多様性を豊かにしているのだと気づかされました。あとでヴィンセントさんが、「彼女は妊娠していた」と教えてくれました。おなかの痛みとは、そういう意味だったのです。彼女の無事を祈りながら、文化もまた世代を超えて受け継がれる ―― まるでオシフィマが人から人へ分かち合われるように― ― と実感しました。

ナミビアは絵はがきのような風景だけではありません。ヴィンセントさんのように、シンプルなおかゆから一日を始める人々がいて、その物語こそが砂漠の心を映しています。
朝ごはんというささやかな存在が、文化や人々をつなぐ窓口になります。ナミビアの人々にとって「一杯のおかゆ」は、その国のたくましさや伝統、そして多様性の中のつながりを映し出しているのです。
さらにナミビアは言語の面でも多様性がきわ立っていて、ヒンバ族のヘレロ語に加え、ダマラ語のように「4種類のクリック音」を使って話すユニークな言語も存在します(実際の音はこちらの動画で確認できます)。1つの国に複数の言語が共存している姿は、まさに多様性を体現しており、ほぼ単一言語国家である日本にとっても、世界の広さと多様さを”朝ごはん”から垣間見るきっかけになるでしょう。
次の「世界の朝ごはんめぐり」では、どの国のだれの朝食に出会えるでしょうか? どうぞ、お楽しみに!
★ヴィンセントさんのFacebook: Heskidus Vincent Kasaona

| 岡本啓史 おかもとひろし🟡国際教育家、生涯学習者、パフォーマー 世界5大陸で暮らし、国連やJICAを通じて50カ国以上で教育支援に携わる。ダンサー、俳優、星付きレストランのシェフ、教師など多彩な経歴を持つ。 異文化で学び続けた海外18年を経て、2024年に帰国し、神戸でグローバル学び舎3L-ミエルを設立。「多様性と幅広い学び」を次世代へつなぐことを使命に、教育、食文化からウェルビーイングなど幅広いテーマで講演・研修・執筆を行う。5言語で学びに関するブログでゆるく発信中。徳島文理大学特任教授。日本SEL学会理事。 著書『なりたい自分との出会い方』(岩波書店)『せかいのあいさつ』全3巻(童心社)監修。 サイト/SNS:https://linktr.ee/mdhiro |